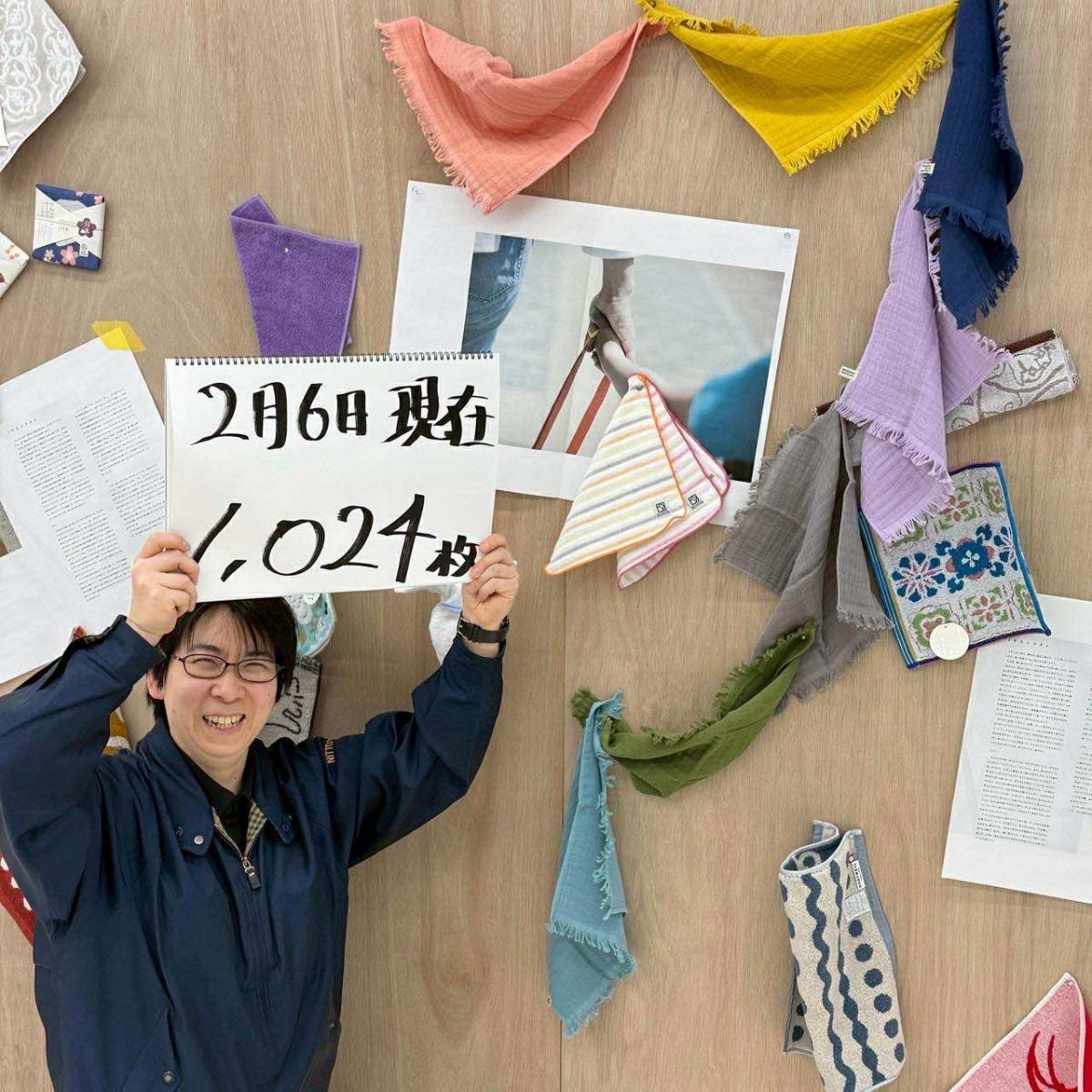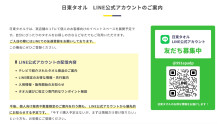「日本橋とやま館」(中央区日本橋室町1)の交流スペースで8月11日、「おわら風の盆体験会」が開かれた。
同館で8月1日~28日に行う特別展示企画「富山の秋まつり」の一環。会期中、「城端むぎや祭」「おわら風の盆」など、富山各地の祭り文化を紹介する展示や越中八尾の特産品の販売を行う。
体験会は昼の部(14時~15時、定員20人)と夜の部(18時~19時30分、定員24人)の2部制で行った。昼の部は八尾の特産品土産付き、夜の部は地酒「風の盆」と富山のつまみ付きで、いずれも満席となった。
出演は富山県民謡越中八尾おわら保存会で、11の保存会支部の中から「鏡町」のメンバーが参加。9月1~3日に富山県八尾町で行われる本番を前に、民謡「越中おわら節」と男踊り、女踊り、昔から伝わる「旧踊り」を披露した。
はじめに同保存会副会長で胡弓(こきゅう)奏者の橘賢美さんが踊りの歴史や背景、魅力を解説。橘さんによると、「おわら風の盆」は江戸時代の1702(元禄15)年に始まったとされ、町建御墨付再取得を祝うため三日三晩踊り明かしたことを起源に持つという。歴史は今も受け継がれ、哀調を帯びた胡弓や三味線の音色、男女の優雅な踊りとともに、夜には石畳にともるぼんぼりが幻想的な雰囲気を作り出し、コロナ禍前は3日間で30万人を超える観光客でにぎわっていたという。
「踊り方教室」では、三味線奏者の杉江宏之さんが「旧踊り」の所作の意味や手の振り方、足の運びなどの基本を指導。最後は保存会員とともに参加者全員で輪になって踊った。
踊りの後に行われた交流会では、ホタルイカの素干、白エビの豆かまぼこ、棒sスティックチーズなど富山の珍味とともに八尾町の地酒「風の盆」が参加者に振る舞われた。
橘さんは「『越中おわら節』の歌詞は5000種類あるといわれているが2年後の保存会100周年までに、埋もれている歌詞を掘り起こして、少しでも皆さまに披露したい」と話す。