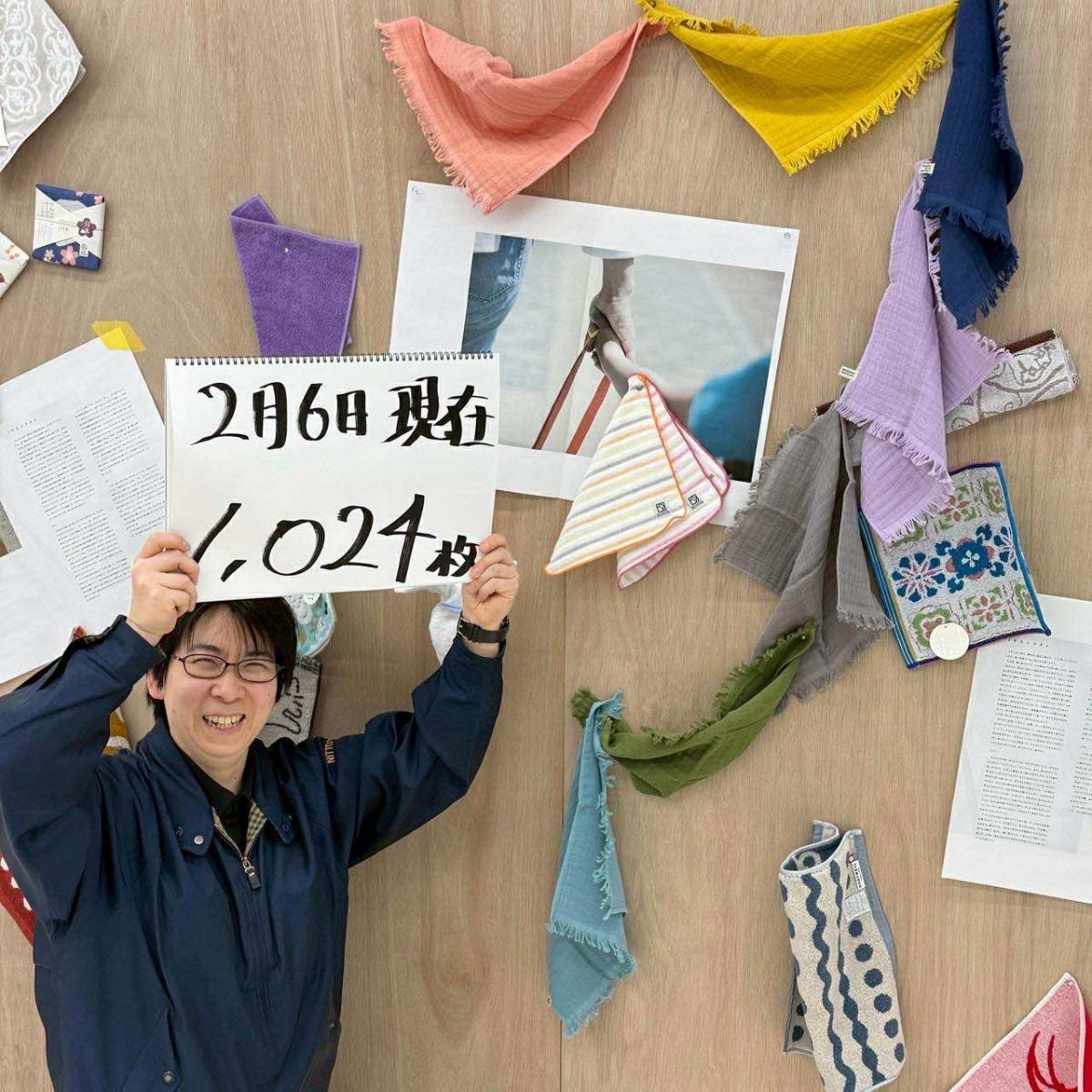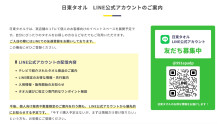日本橋学生工房が11月25日、写真展「Still Nihonbashi ― うつりゆくまちに、繋(つな)がる記憶 ― 展」が画材店「有便堂」(中央区日本橋室町1)と日本橋三越本店Mステージで始まった。
有便堂は1912(大正元)年に初代石川祐造さんが東京九段下から和紙、筆、墨などを風呂敷に包み外商を始め、1916(大正5)年に湯島で画材店として創業。東京大空襲で店舗が消失したことを受け、1946年に現在の室町小路(三越本館向かい)へ移転した。湯島時代から横山大観、平山郁夫、藤田嗣治など日本美術史を代表する画家が画材を求めて訪れたという。室町小路の店は、元は麩製造工場だった建物を引き継いで使ってきたが、近隣の再開発に伴い、7月末に現店舗での営業を終了。現在はオンラインや電話などで販売を続けている。
同展を企画した日本橋学生工房は、現役学生と大学院生15人で組織する任意団体。2002年の創設以来、日本橋での清掃活動や祭りの手伝い、常盤小学校でのボランティア授業など、学生らしい視点を生かした地域活動を続けてきた。今回の展示では、工房の現メンバーと歴代メンバーが街並みや地域の人々を写した写真を紹介する。
工房第23期代表の黒部真由さんは「私たちが日本橋とどう関わり、街がどのように私たちを受け入れてくれたかを見ていただける展示。町会の方々や企業の方々をはじめ、日本橋にゆかりのある方に足を運んでいただきたい。同世代の若い人たちにも、写真展を通じて日本橋の魅力を知ってほしい」と話す。
有便堂4代目店主の石川朋季さんは「(日本橋は)地域コミュニティーが強く、安心して商売ができた。お客さまは老舗とのつながりを重視し、店の人と会話する文化が残っている」と話す。「店から見えていた景色が変わってしまうのは名残惜しい。再開発は前向きに受け止めているが、路面店ならではのつながりが失われることには寂しさもある」とも。
黒部さんは「写真展で最も大切にしたいのは、副題にある『うつりゆくまちに、つながる記憶』。室町エリアでは12月1日から再開発工事が始まるが、人々の記憶はこれからも残り続ける。再開発の是非を問うものではなく、そこにあった景色や営みが確かに存在したことを伝えたい」と話す。「写真を通して自身の記憶と重ね合わせ、誰かと語り合うことで、新たな日本橋を思い描くきっかけになれば」と来場を呼びかける。
開催時間は11時~16時。入場無料。11月29日まで。