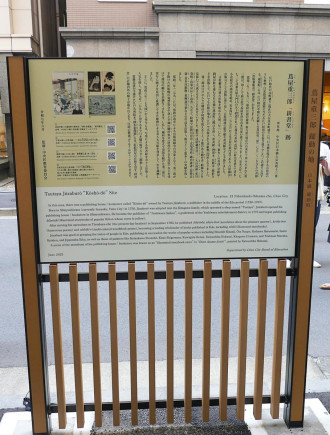江戸文化を学ぶ市民講座「第6回蔦重(つたじゅう)勉強会」が9月13日、日本橋の常盤小学校(中央区日本橋本石町4)別館体育館で開催された。主催は地元町会有志などで組織する「蔦屋重三郎を学ぶ日本橋の会」。
NHK大河ドラマ「べらぼう」主人公の蔦屋重三郎が開業した地本問屋「耕書堂」が日本橋の通油町(とおりあぶらちょう:現日本橋大伝馬町)にあったことから、地元町会有志が昨年7月に立ち上げた同会。江戸時代に浮世絵師・喜多川歌麿や東洲斎写楽らを世に送り出した版元の蔦屋重三郎を切り口に、当時の日本橋で培われた文化を学ぶ。
第6回となる今回は、歴史ライターで「かしまし歴史チャンネル」を配信する歴史系YouTuberとしても活動する川合章子さんが登壇。「江戸四大名物と日本橋の名店」と題し、うなぎ、そば、寿司、天ぷらといった江戸食文化と日本橋の老舗が果たしてきた役割について解説した。
庶民に親しまれた料理がどのように広まり、現代の日本橋に受け継がれているかを、老舗のエピソードを交えて紹介。会場には200人を超える地域住民や歴史ファンらが駆け付けた。
川合さんは「食文化は単なる味覚の楽しみではなく、まちの暮らしや人々のつながりを映す鏡」と話し、当時の庶民が味わった料理と現代の名店が結びつく歴史的背景を解き明かした。参加者は熱心に耳を傾け、質疑応答の時間には活発なやり取りが交わされた。
勉強会の運営を担う事務局は「地域の歴史を身近に感じるきっかけにしてほしい」と話す。次回の勉強会は12月6日を予定する。